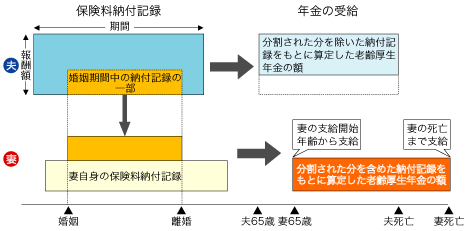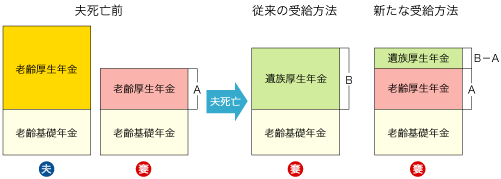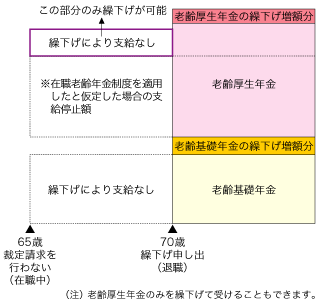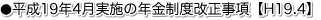 |
|
| 平成16年に公布された年金制度改正法に基づき、平成19年4月から、離婚時等の厚生年金の分割、遺族年金制度の見直し、在職老齢年金の適用拡大、老齢厚生年金の繰下げ、申し出による年金の支給停止がはじまります。 |
|
|
|
|
平成19年4月1日以降に離婚等をした場合、当事者間の合意または裁判所の決定がある場合、2分の1を上限として婚姻等期間中における厚生年金保険の保険料納付記録(標準報酬額)を分割できるようになりました。
分割は標準報酬額の多い人から少ない人へのみ行うことができ、それぞれ自分自身の厚生年金の受給資格に基づき、分割後の保険料納付記録に応じた年金を受けます。すでに年金を受けている人から分割を受けても、生年月日による自分自身の支給開始年齢に達するまでは支給されません。また、分割された保険料納付記録は、厚生年金の額の算定の基礎となりますが、年金受給資格期間等には算入されません。
この厚生年金の分割は施行日以降の離婚が対象となりますが、施行日前の婚姻等期間中の保険料納付記録についても分割の対象となります。分割の請求は、離婚等から2年以内に行う必要があります。 |
|
| ※保険料納付記録の分割を行った元の配偶者が死亡しても、分割を受けた人の年金受給には影響ありません。 |
|
| ■離婚時の厚生年金の分割における保険料納付記録と年金受給のイメージ |
|
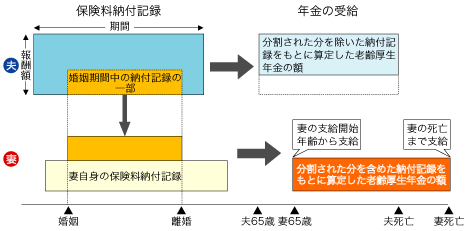 |
|
|
|
|
| 社会保険庁では、離婚等の当事者双方または一方からの請求により年金分割のための情報提供を行っています。情報提供は「年金分割のための情報提供請求書」を社会保険事務所に提出することで受けられます。当事者双方からの請求があった場合や離婚等をしている場合は双方に、離婚等をしていない当事者の一方が請求した場合には本人のみに「年金分割のための情報通知書」により情報提供が行われます。情報提供の内容は、(1)分割の対象期間、(2)分割の対象期間に係る離婚当事者それぞれの標準報酬総額、(3)按分割合の範囲等です。 |
|
厚生年金基金の基本年金の代行部分についても分割の対象となります。分割により加入員の標準報酬額が減る場合は、分割後の減額された標準報酬額に基づいて基金から代行部分を支給します。また、分割により加入員の標準報酬額が増える場合は、基金が支給する代行部分の額は変わらず、増額分は国から支給されます。
なお、基本年金のプラスアルファ部分と加算年金については分割の対象となりません。
|
|
|
|
|
|
|
| ○高齢期の遺族配偶者に対する遺族厚生年金と老齢厚生年金の併給の見直し |
|
| 65歳以降の遺族配偶者について、本人が納めた保険料をできるだけ年金給付に反映させるため、自分の老齢厚生年金を全額受給した上で、改正前の水準の遺族厚生年金と差額があれば、その額が遺族厚生年金として支給されるしくみになりました。 |
|
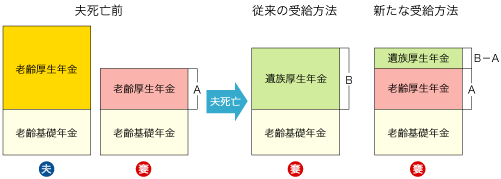 |
|
| ○中高齢寡婦加算の見直し |
|
| 夫の死亡時に35歳以上の妻に40歳から支給されていた中高齢寡婦加算(遺族基礎年金を受けられない子のいない妻に支給)が、待期期間をなくし夫の死亡時に40歳以上65歳未満の妻への支給になりました。 |
|
| ○若齢期の妻に対する遺族厚生年金の見直し |
|
| 夫の死亡時に30歳未満で子のいない妻に対する遺族厚生年金が5年間の有期給付となりました。 |
|
| ※子とは18歳の年度末まで(1・2級障害の場合は20歳未満)の子をいいます。 |
|
|
国の遺族年金制度の見直しに伴う、基金の年金についての変更はありません。
|
|
|
|
|
|
|
在職者の年金額と給与等に応じて年金額を調整する在職老齢年金制度は、従来、60歳以上70歳未満の人が対象とされていました。平成19年4月からは、70歳以上の在職者にも60歳代後半の在職老齢年金と同様のしくみ(基本月額と総報酬月額相当額※の合計が48万円を超える場合はその2分の1を支給停止)が適用されます。
ただし、70歳以上の在職者は在職老齢年金のしくみの適用のみで、厚生年金保険の被保険者とはならないため保険料の負担はありません。 |
|
| ※その月の標準報酬月額とその月以前1年間に受けた標準賞与額の12分の1の合計額。 |
|
|
当基金では、60歳代後半の在職者に対して在職老齢年金制度による基本年金(代行部分+プラスアルファ部分)の支給調整を行っていますが、70歳以上の在職者についても同様に支給調整を行います。
|
|
|
|
|
|
|
老齢厚生年金は65歳から支給されますが、今後は高齢者の就労がより一層進んでいくことが見込まれるとともに、実際に引退した年齢から年金を受けることを望む人が増えていくことも考えられます。そこで、平成19年4月から、老齢厚生年金を受ける年齢を自分自身で選択できるように、65歳以降の老齢厚生年金の繰下げ制度が導入されることになりました。この制度では、老齢厚生年金を66歳になる前※に請求しなければ、希望した時期から増額(繰下げ1月につき0.7%)された年金を繰り下げて受けることができます。
なお、65歳以降の老齢厚生年金の繰下げ制度は、施行日(平成19年4月1日)前に老齢厚生年金の受給権が発生している人は対象となりません。
※65歳を過ぎてから受給権が発生する人は、受給権発生から1年以内。 |
|
| ■老齢厚生年金を70歳に繰下げ申し出する場合のイメージ |
|
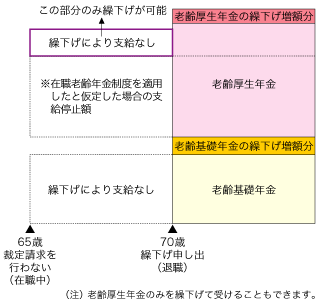 |
|
|
|
|
国の老齢厚生年金の繰下げ支給の申し出があった場合、基金の基本年金(代行部分とプラスアルファ部分)についても繰下げ支給を行います。 なお、加算年金については繰下げ支給を行いません。
|
|
|
|
|
|
|
年金受給権者本人の申し出により、年金の支給停止を行うことができます。この申し出をした場合、年金の全額が支給停止されますが、一部のみの支給停止を行うことはできません。また、在職老齢年金制度により、すでに年金額の一部が支給停止されている場合は、残りの支給されている部分について支給停止することができます。
年金の支給停止は本人の意思に基づいていつでも撤回することができますが、すでに支給停止された年金額について、過去にさかのぼって受けることはできません。 |
|
国の年金について支給停止の申し出があり、これとは別に基金へも年金の支給停止の申し出があった場合、基金の基本年金(代行部分とプラスアルファ部分)についても支給停止を行います。
なお、加算年金については支給を行います。
|
|
|
|